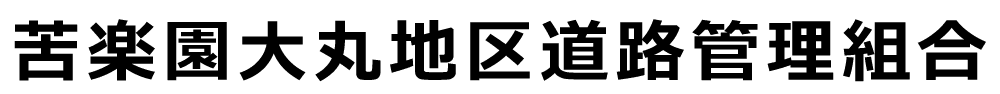これまでの経緯と課題
苦楽園大丸地区は、1960年に旧大丸土地株式会社が開発・分譲を開始した住宅地です。大丸地区の造成着手後に「宅地造成等規制法」が制定されました。当時、既に着手済みの開発については、届出を行うことで条件を満たすこととされ、この地区でも県による現地視察を経て、当時の基準に基づいた届出が県本庁および土木出張所の2箇所に提出されました。しかし、開発時期が現在運用されている住宅地開発に関わる様々な法律等が整備される以前であったため、現在の行政移管基準を満たさない仕様となっていました。
さらに、過渡期に開発された住宅団地に対する、その後の行政指導が行われなかったことから、開発当時の基準のまま現在に至っています。加えて、2001年に旧大丸土地株式会社が倒産したことにより、生活に必要な道路・水道・橋などのインフラや、未販売の急傾斜地の管理が地域住民に委ねられることとなりました。
水道施設については、住民が1世帯あたり8万円から89万円を負担し、2005年に西宮市への移管が完了しました。
しかし、現在も残る道路等の維持管理が大きな課題です。特に、道路・橋・雨水管の行政への移管には、市の現在の基準を満たすための大規模な調査・改修工事が必要となります。この費用は莫大で、住民が全てを負担することは現実的ではありません。組合は長年にわたり市との交渉を続けていますが、法的な壁は厚く、難航しています。
今後の課題は、まず行政が求める調査・改修費用の正確な把握です。その上で、行政には、この地域が開発法制度の未整備な時代に開発された特殊性や、私道の距離(約2.7キロメートル)が非常に長い実情を理解していただくよう働きかけていきます。そして、基準の緩和や財政的支援など、行政の特別な判断により、住民負担が最小限に抑えられるよう交渉を継続していくことが、組合に課せられた現実的な課題です。
組合費について
この地が開発され60年以上が経過し、インフラの老朽化は進んでおり、2010年には道路の陥没事故も発生するなど、事故のリスクも高まっています。このような日々発生の可能性のある事故への対応や、将来の移管に向けた工事に必要な費用は、不可欠です。
この道路等の維持管理費用については、その経緯から実質的に地域の土地所有者の共有物であるという認識のもと、土地所有者が負担する必要があります。 この法的根拠として、民法第253条が「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」と規定しています。
そのため、現在、新しくこの地に転入される方には、初期負担金として20万円、また組合費として月額3千円(年額3万6千円)を徴収し、管理費に充てています。これは、この地に住む住民全員の責務であるという認識に基づいています。
管理組合と有限会社設立の経緯
住民は2001年に「苦楽園大丸地区 水道道路管理組合」を結成し、道路・水道・橋などのインフラを引き継ぎました。この際、引き継いだ道路や急傾斜地などの不動産を、住民個々に登記することはその数の多さから現実的ではありませんでした。
そのため、組合の下に有限会社を設立し、その有限会社名義で登記を行いました。また、2005年に水道施設の移管完了後、「苦楽園大丸地区水道道路管理組合」を「苦楽園大丸地区道路管理組合」(管理組合)と改称し現在に至っています。
これまでの歩み
| 1960年(昭和35年) | 「株式会社大丸土地」開発分譲開始 | |
| 2001年(平成13年) | 5月 | 「株式会社大丸土地」自己破産申請 |
| 同年 | 5月 | 「苦楽園大丸地区水道道路管理組合」設立 |
| 同年 | 11月 | 破産管財人⇔「水道道路管理組合」間で水道設備一式の無償譲渡契約を締結。 |
| 同年 | 11月 | 道路部分の受け皿として住民有志からなる「有限会社苦楽園大丸地区管理会社」設立 |
| 同年 | 12月 | 破産管財人⇔「有限会社」(菅原代表)間で私道、急傾斜地の売買契約を締結 |
| 2004年(平成16年) | 水道の西宮市への移管完了 | |
| 2005年(平成17年) | 「苦楽園大丸地区水道道路管理組合」を廃止し、「苦楽園大丸地区道路管理組合」を新たに設立 (現在にいたる) | |
| 2014年(平成26年) | 西宮市が当管理組合に対し4つの案を提示 | |
| 2017年(平成29年) | 西宮市が当管理組合に対し上記の4つの案の内のB案(管理協定案)において、側道・雨水管・道路法面(のりめん)を対象からはずす事を表明 | |
| 2022年(令和 4年) | 当管理組合が西宮市に対し、”すべての私道の市への移管”(A-2案)が住民の総意である事を表明 | |
| 2023年(令和5年) | 西宮市が当管理組合に対し、私道の市道への移管の要望書について(回答)を提示。 |